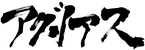農業に役立つ土壌学2 土壌生物
1.多様な土壌生物
土壌生物という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、生物多様性はどこかで聞いたことがあるでしょう。2022年12月にカナダ・モントリオールで開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、2030年に向けて陸と海の30%以上を保全する「30by30目標」など、新たな生物多様性保全を目指す目標が定められました。「生物多様性(Biodiversity)」という言葉は、守るべき大切なものだという意味とともに、身近なものとなっています。「生物多様性」と聞いて思い浮かべるのは、アフリカ大陸のサバンナに生息するさまざまな動物たち、大小さまざまな植物が繁茂する身近な森林や、魚が豊富な海だったりするかもしれません。しかし、土も多様な生物が生息する環境の一つです。1gの土には、十億もの細菌と200mにも及ぶ糸状菌の菌糸、そして多様な土壌動物が含まれると言われています (図1) (FAO, 2021)。
ところで、十億もの細菌は何種類から構成されているのでしょうか。目に見える動物や植物であれば主に形態に基づき種を同定することが可能です。しかし、大半が目に見えず培養もできない土の細菌の場合は簡単ではありません。この難題を解決するために、土から抽出したDNAを用いて種数の推定が行われました。2本鎖DNAを高温処理で1本鎖としてから50℃にすると、1本鎖DNAは徐々に2本鎖に戻ります。このとき、構成されるDNAの種数が増えるほど2本鎖に戻るまでの時間を要するという原理から、1gの土に4000種類の細菌が含まれることが推定され(Torsvik et al., 1990)、土の生物はきわめて多様であると世界に衝撃を与えました。近年、次世代シークエンサーの発展にともない土の生物の多様性の全貌がわかりつつあります。アマゾンの森林土壌や根圏(植物の根の周りの土)には3000~5000種類の細菌が生育していることが報告され(Fonseca et al., 2018)、Torsvikらの推定が間違っていなかったことが明らかになりました。
地球上に生息する種のうち、どの程度の種が土を棲み処としているのかを調べた研究によると、一生のうちのある時期のみ土に生息するものも含めると、地球上の種の2/3は土に生息していることが報告されています(Anthony et al., 2023)。その中でもっとも土に生息している割合が高かったのは、99%の種が土に生息していると推定されたヒメミミズ(環形動物門Annelida、貧毛網Oligochaeta、ヒメミミズ科Enchytraeidae)という体長2~20mmほどの小型のミミズでした(99%)(図2)。ミミズが土を豊かにすることは良く知られますが、ヒメミミズもミミズと同じような役割を小規模に果たすことが知られています(Römbke et al., 2017)。著者らの調査では、対象とした37圃場のうち約90%の農地でヒメミミズの生息が確認されており(未発表)、日本の農地に広く生息していることが明らかになりつつあります。他にも、カビ(90%)やミミズ(63%)も多くの種が土に生息しており、細菌や線虫、原生生物は種全体の半分ほどが土を棲み処としています(それぞれ51%、43%、41%) 。もっとも少なかったのが哺乳類でしたが(4%)、幅広い生物が土を棲み処とし、そして多様な生態系が形成されていることがわかります。

図1 土1に含まれる土壌生物
((FAO 2021)をもとに作成)

図2 ヒメミミズ
(“A CHAOS OF DELIGHT”より引用)
https://www.chaosofdelight.org/enchytraeidae-1
2.土壌生物の構成員 -土壌微生物と土壌動物-
2.1. 土壌微生物
微生物は主に①細菌、②アーキア、③糸状菌、④原生生物、の4種類に分けられます(図3)
細菌は0.5~2μmほどの大きさの原核生物で、丸い球菌(coccus)や細長い形をした桿菌(rod)などさまざまな形のものがあります。後述する糸状菌のように菌糸を形成し、さまざまな抗生物質を生産することで有名な放線菌は、細菌の仲間です。細菌は、特に有機物や無機物の化学的な変化に寄与しており、有機物を植物が利用可能な形に変える「無機化」や、二酸化炭素や亜酸化窒素といった温室効果ガスの発生などに関係しています。頻繁に耕され、作物が栽培されない期間がある畑では、森林と比べて植物と共生する糸状菌などが減り、細菌が中心となる特徴があります。
細菌と同様に原核生物であるアーキアは、見た目が細菌と似ていることから「古細菌」と呼ばれていましたが、遺伝子を用いた解析により、細菌とも真核生物とも異なるドメインを形成することがわかっています。高温や強酸性・アルカリ性などの極限環境に生育するものが多いことが特徴ですが、農耕地などにも生育しており、農業分野で有名なメタン生成菌はアーキアに含まれます。
真核生物である糸状菌は、菌糸を伸ばして生育し、それらが集まった菌糸体を作ります。植物の約8割と共生するといわれるアーバスキュラー菌根菌はこの仲間です。有性生殖をする「完全菌類」と呼ばれるグループの中には子実体を作るものがいて、これがいわゆるキノコです。一方で、有性生殖が確認されていないものは「不完全菌類」と呼ばれ、無性生殖を行います。糸状菌は特に植物遺体などの有機物分解に貢献しています。
原生生物は真核生物のうち糸状菌でも植物でも動物でもない生物の総称で、系統的に多様なグループを含みます。光合成によって酸素を発生する藻類、鞭毛虫や繊毛虫などの生物群に代表されます。藻類の一種でありラン藻とも呼ばれるシアノバクテリアには窒素固定をする種があることも知られていますが、これは分類的には細菌に含まれます。

図3 土壌微生物
2.2. 土壌動物
土壌動物は体の大きさによって、小さい方から①小型土壌動物、②中型土壌動物、③大型土壌動物、④巨大土壌動物の4つのグループに分けられます(図4)。

図4 土壌動物((FAO, 2021)を基に作成)
頻繁に耕される畑では体の大きな土壌動物は棲むことができないため、小型・中型土壌動物が主に生息しています。代表的な土壌動物である線虫は植物に病気を引き起こす植物寄生性線虫がよく知られますが、実はその多くは「自由生活性(自活性)線虫」という、微生物や土壌動物を餌とするものです。これらの線虫は、微生物の働きを促進することが知られており、微生物と一緒に土壌機能を支えています。また、体が大きな土壌動物は、有機物を細かく砕いて微生物の分解を促進したり、孔隙や団粒を作って物理性を改善するなど、微生物にはない生態系改変者(ecosystem engineers)としての働きも担っています。動画はヒメミミズが植物残渣を摂食している様子を示しています(図5)。
図5 残渣を食べるヒメミミズ
3.土壌生物と土壌機能
土壌生物は様々な土壌機能を支えています。機能は、①炭素・気候調整、②水分調整、③養分循環、④病害防除、に大きく分けられ、それぞれにおいて、土壌生物が様々な形で貢献しています(図6) (Creamer et al., 2022)。たとえば養分循環では、まずヒメミミズや草食性のダニが有機物を細かくし、さらにそれらを細菌や糸状菌が分解し、植物が利用できる形に変化させます(無機化)。また、微生物を餌とする原生生物や線虫が、微生物を捕食することで有機物の無機化が促進されることも知られています。
病害防除においては、原生生物や線虫、トビムシやダニなどが、病原菌や植物寄生性線虫を直接捕食することに加え、細菌や糸状菌は毒性物質を産出し、それらの生育を抑止することもあります。また、微生物が植物の根に働きかけることで植物自身の病害抵抗性を高めることも知られています。
このように、様々な生物が直接的、間接的に寄与することで、土壌機能を支えています。

図6 土壌生態系機能
((Creamer et al. 2022)をもとに作成)
4.土壌生物の多様性と土壌機能
生態学では、多様性が高いほど、①生態系機能に強く影響する種が含まれる確率が上がるため、そして、②資源利用の効率が高くなるため、生態系機能が高まることが知られています。
土壌生態系でも、多様性と土壌機能の関係について様々な研究が行われてきました。生態学の知見と同様に、微生物(細菌と糸状菌)の多様性が高いほど異なる機能に貢献する微生物が増えるため、リター分解や植物への窒素やリンの供給といった土壌機能が向上します(Wagg et al., 2019)。また、菌根菌や線虫などさらに多様な生物の存在によって、炭素隔離や窒素無機化が高まり、逆にリンの溶脱やN2O発生が抑えられるといった報告もあります(Wagg et al., 2014)。さらに、農地にミミズがいることで作物収量が25%向上するなど(van Groenigen et al., 2014)、微生物間や土壌生態系全体で、幅広い役割を持つ生物が多様に存在するほど土壌機能が高まることがわかっています。
多様性にはもう一つの側面があります。それが、「冗長性(redundancy)」や「回復力(resilience)」です。これは、乾燥や攪乱などのストレスを受けた時に、土壌機能を維持あるいは回復させる力です。たとえば、同じ土壌機能を支えている生物でも、種によって乾燥などストレスへの耐性が異なります。そのため、多様な種によって一つの土壌機能が支えられている土ほど、土がストレスを受けた時に機能を保ちやすくなります。また、たとえストレスを受け一時的に機能が低下したとしても、機能が回復しやすくなります。実際に、微生物の多様性が高いほど、同じ土壌機能に貢献する微生物種が増え、冗長性が高まることがわかっています(Wagg et al., 2019)。また、一次生産者である藻類、分解者である細菌、消費者である原生生物からなる群集で、各機能群の種数を操作した研究例では、多様な群集ほど生産力と安定性が高まりました(Naeem and Li, 1997)。さらに、著者らの研究例では、堆肥を連用した土壌では化学肥料のみを連用した土壌に比べて微生物の多様性が高まり、乾燥や凍結融解、土壌消毒といったストレスから土壌生物機能が回復しやすいことがわかりました(Wada and Toyota, 2007)。
多様性を表わす用語の1つに均衡度(均等度:evenness)があります。均衡度は、どれだけ各種が同じ比率で存在するかを示し、同じ種数からなる集団でも、優占種がおらずより均等な割合で構成されている集団ほど高くなります。いずれも18種からなり、異なる構成割合の脱窒細菌群集の脱窒能を比較したところ、ストレスがない条件下では均衡度と脱窒能には関係がなかったものの、塩ストレス下では均衡度が高いほど脱窒能の低下が緩やかとなりました(Wittebolle et al., 2009)。このことから、多様性が高いだけではなく、均衡度の高さも冗長性および回復力に需要であることが明らかになりました。気候変動によって気温や降水量が不安定な今、多様な生物相を支える土壌環境を作り、冗長性や回復力を高めることが重要だと言えます。
では、どのように多様な、そして高い土壌機能を支えるような生物相を形成できるのでしょうか。まだこの問に対する明確な答えは見つかっていません。しかし、複数作物の栽培(Cappelli et al., 2022)、堆肥の施用や減耕起などが有用(Cozim-Melges et al., 2024)とされています。前者については、植物の種類によって土壌微生物群集に与える影響が異なることから、混植などによる複数作物の栽培によって土壌微生物が多様になります(Cappelli et al., 2022)。また、堆肥施用に関しては、土壌肥沃度を高め植物生育を促進することはよく知られ(もちろん使い方によっては逆効果になることもあります)、前述のように土壌機能の冗長性が向上した例があります。一方、耕起は様々な生物に影響を与え、特に菌根菌を含む糸状菌の菌糸を切断してしまうことで、農地を細菌を中心とした土壌生物相へと変えます。糸状菌が多い土壌は細菌が多い土壌よりも窒素を保持する能力が高く、窒素の溶脱やN2O発生が抑えられることが知られています(Thiele-Bruhn et al., 2012)。また、土を豊かにする働きが有名なミミズも、耕起によって姿を消してしまいます。以上のことから、耕起は有用な生物が棲みにくい土にしてしまうという側面があるとわかります。こういった視点から、有機農業は必ずしも土壌生物に優しい農業ではないと言える(金子、 2023)ということは、留意すべき点です。土壌生物が持つ機能を最大限に活かし、農薬や化学肥料の使用量を減らすにはどのような管理を行えば良いのか、これは今後の重要な課題です。
次回は、土壌微生物に焦点を当てて、農業における働きについて詳しく見ていきます。
関連記事
連載第1回 農業に役立つ土壌学1 土壌学とは
連載第3回 農業に役立つ土壌学3 土壌微生物
引用および参考文献
Anthony, M.A., Franz Bender, S., van der Heijden, M.G.A., 2023. Enumerating soil biodiversity. PNAS 120. doi:10.1101/2023.02.12.528215
Cappelli, S.L., Domeignoz-Horta, L.A., Loaiza, V., Laine, A.-L., 2022. Plant biodiversity promotes sustainable agriculture directly and via belowground effects. Trends in Plant Science 27, 674–687.
Cozim-Melges, F., Ripoll-Bosch, R., Veen, G.F.C., Oggiano, P., Bianchi, F.J.J.A., van der Putten, W.H., van Zanten, H.H.E., 2024. Farming practices to enhance biodiversity across biomes: a systematic review. Npj Biodiversity 3, 1.
Creamer, R.E., Barel, J.M., Bongiorno, G., Zwetsloot, M.J., 2022. The life of soils: Integrating the who and how of multifunctionality. Soil Biology & Biochemistry 166, 108561.
Fonseca, J.P., Hoffmann, L., Cabral, B.C.A., Dias, V.H.G., Miranda, M.R., Martins, A.C.D.A., Boschiero, C., Bastos, W.R., Silva, R., 2018. Contrasting the microbiomes from forest rhizosphere and deeper bulk soil from an Amazon rainforest reserve. Gene 642, 389-397.
Food and Agriculture Organization, 2021. State of knowledge of soil biodiversity: status, challenges and potentialities, report 2020. Food & Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy.
金子信博. 2023. ミミズの農業改革. みすず書房. 東京 Naeem, S., Li, S., 1997. Biodiversity enhances ecosytem reliability. Nature 390, 507-509.
Römbke, J., Schmelz, R.M., Pélosi, C., 2017. Effects of Organic Pesticides on Enchytraeids (Oligochaeta) in Agroecosystems: Laboratory and Higher-Tier Tests. Frontiers of Environmental Science & Engineering in China 5. doi:10.3389/fenvs.2017.00020
Thiele-Bruhn, S., Bloem, J., de Vries, F.T., Kalbitz, K., Wagg, C., 2012. Linking soil biodiversity and agricultural soil management. Current Opinion in Environmental Sustainability 4, 523–528. Torsvik, V., Goksoyr, J., Daae, F. L., 1990. High diversity in DNA of soil bacteria. Applied and Environmental Microbiology 56, 782-787.
van Groenigen, J.W., Lubbers, I.M., Vos, H.M.J., Brown, G.G., De Deyn, G.B., van Groenigen, K.J., 2014. Earthworms increase plant production: a meta-analysis. Scientific Reports 4, 6365.
Wada, S., Toyota, K., 2007. Repeated applications of farmyard manure enhance resistance and resilience of soil biological functions against soil disinfection. Biology and Fertility of Soils 43, 349-356.
Wagg, C., Bender, S.F., Widmer, F., van der Heijden, M.G.A., 2014. Soil biodiversity and soil community composition determine ecosystem multifunctionality. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111, 5266–5270.
Wagg, C., Schlaeppi, K., Banerjee, S., Kuramae, E.E., van der Heijden, M.G.A., 2019. Fungal-bacterial diversity and microbiome complexity predict ecosystem functioning. Nature Communications 10, 1–10.
Wittebolle, L., Marzorati, M., Clement, L., Balloi, A., Daffonchio, D., Heylen, K., De Vos, P., Verstraete, W., Boon, N., 2009. Initial community evenness favours functionality under selective stress. Nature 458, 623-626.