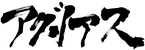バイオスティミュラントと肥料の違いをわかりやすく解説!正しい理解と使い方
農業界で注目されている「バイオスティミュラント」。一体どんなもので、長年使われてきた「肥料」とはどう違うのでしょうか?
近年、肥料価格の高騰が続き安定生産への関心が高まる中、バイオスティミュラントはコスト削減や生産性向上の新たな選択肢として期待されています。しかし、その力を最大限に活かすには、肥料との違いを正しく理解することが不可欠です。
この記事では、バイオスティミュラントと肥料の基本的な役割から、違い、メリット・デメリットまでを、わかりやすく具体的に解説します。
バイオスティミュラントとは
バイオスティミュラントについて理解するために、まずはその基本的な定義から見ていきましょう。
定義と基本概念
|
効果 |
詳細 |
|
根の発達促進 |
根をしっかりと張り巡らせることで、水や養分を効率よく吸収できるようになります。 |
|
非生物性ストレスの耐性強化 |
・気象ストレス 高温、低温、干ばつ(水不足)、多湿、日照不足など、植物にとって過酷な気象条件に耐える力を向上させます。 ・土壌ストレス 塩分濃度が高い土壌(塩害)や、養分の偏りがある土壌でも、生育しやすくします。 |
|
養分の利用効果の向上 |
土壌中の養分や施肥した肥料分を、植物がより無駄なく吸収・利用できるようにサポートします。 |
|
作物の品質向上 |
果実の糖度や酸度、色づき、大きさ、形状、収穫後の日持ちなどを改善する効果が期待できます。 |
|
土壌の健康促進 |
土壌中の有用な微生物の活動を活発にしたり、有機物の分解を助けたりすることで、植物が育ちやすい豊かな土壌環境を作る手助けをします。 |
また、国際的な定義として定められているのも特徴です。
FAO(国連食糧農業機関)では「植物の生理活性を高めるもの」として規定されていたり、欧州連合(EU)では、農薬や肥料とは別カテゴリの農業資材として正式に認定されていたりします。
バイオスティミュラントの主な種類
バイオスティミュラントにはさまざまな種類があり、使用目的や作物の種類によって選択が重要です。
|
種類 |
物質 |
主な効果 |
|
微生物資材 |
光合成細菌、乳酸菌、酵母菌といった、植物や土壌にとって有益な働きをする生きた微生物、またはその培養液や代謝物を利用した資材。 |
リン酸など土壌中で吸収されにくい養分の可溶化(植物が吸える形に変える)や供給を助けたり、根の伸長を促進したりします。
また、植物ホルモン様物質を生成したり、土壌の病原菌の増殖を抑えたり、土壌構造を改善したりする効果も期待されます。 |
|
海藻(抽出物)資材 |
コンブ、ワカメ、アスコフィルム・ノドサムといった様々な種類の海藻から、有効成分を抽出して作られた資材。
|
植物の免疫力を高めたり、発根を促進したり、細胞分裂を活性化させたり、乾燥や塩害などのストレス耐性を向上させたりする効果が期待できます。 |
|
腐植質 (腐植酸・フルボ酸)資材 |
土壌中の有機物(動植物の遺骸など)が微生物によって長期間分解されて生成する、「腐植」のうち、特定の抽出方法で得られる成分です。
主に、フミン酸(腐植酸)とフルボ酸に分けられます。 |
土壌の物理性(保水性、通気性、団粒構造)を改善する効果が高いのが特徴です。
また、土壌中のミネラルイオンと結合して植物が吸収しやすい形に変えるキレート作用や、陽イオン交換容量(CEC)を高めて土壌の保肥力を向上させる効果、根の伸長を促進する効果に期待できます。 |
|
アミノ酸・ペプチド資材 |
アミノ酸や、アミノ酸がいくつか結合したペプチドを主成分とする資材。 動物由来(コラーゲンなど)や植物由来(大豆など)のタンパク質を、酵素や酸で分解して製造されます。
|
特定の生理活性(光合成促進、気孔開閉調節、ストレス耐性向上など)を持つものが多くあります。
特に、プロリンやグリシンベタインなどは、浸透圧調整物質として乾燥や塩害ストレスから細胞を保護する働きがあります。 |
これらの多様なバイオスティミュラントは、単独で使われることもありますが、複数の種類を組み合わせることで、より幅広い効果や相乗効果を狙うことも可能です。
肥料とは?
農業の基本ともいえる「肥料」について、その役割と種類を改めて確認しておきましょう。
肥料の定義と役割
肥料は、植物が成長するために必要な栄養素を供給し、健全な成長を促す目的で使用される農業資材です。植物が必要とする様々な栄養素を直接的に補給することで、作物の生産性向上に貢献します。
肥料の主成分は以下の通りです。
●窒素(N): 葉や茎の成長を促進し、緑の部分の形成に必要不可欠な要素です。タンパク質合成にも関与します。
●リン(P): 根の発達や花・実の成長を助ける役割があります。エネルギー代謝にも重要な成分です。
●カリウム(K): 病害抵抗力を強化し、光合成を助ける働きがあります。また、水分バランスの調整にも関わります。
これらの三大要素に加え、カルシウム、マグネシウム、硫黄などの中量要素や、鉄、マンガン、亜鉛などの微量要素も植物の健全な成長には欠かせません。
有機肥料と化学肥料の違い
肥料は、その原料や製造方法から、大きく「有機肥料」と「化学肥料(無機質肥料)」の2つに分類されます。それぞれの特徴を理解し、使い分けることが大切です。
<有機肥料>
●堆肥、魚粉、骨粉、油かすなど生物由来の資材
●ゆっくりと分解されるため、効果が持続しやすい
●土壌の物理性や生物性も改善する総合的な効果がある
<化学肥料>
●硝酸アンモニウム、リン酸塩、硫酸カリウムなど化学的に合成された資材
●水に溶けやすく即効性が高い
●必要な栄養素を正確な量で補給できる
有機肥料と化学肥料には、それぞれメリットとデメリットがあります。
「どちらが優れている」という単純な比較ではなく、作物の種類、生育ステージ、土壌の状態、目指す農業のスタイル(慣行栽培、有機栽培など)に応じて、適切に選択したり、両方を組み合わせて(有機化成肥料など)利用したりすることが、上手な施肥管理の鍵となります。
バイオスティミュラントと肥料の違い
バイオスティミュラントと肥料の特徴を踏まえたうえで、それぞれの違いを比べてみましょう。
目的の違い
|
種類 |
バイオスティミュラント |
肥料 |
|
目的 |
植物の生理機能を活性化 |
栄養素の供給 |
|
作用 |
ストレス耐性向上、根の発達促進 |
植物に直接栄養を与える |
|
成分 |
微生物、アミノ酸、フミン酸など |
窒素、リン、カリウムなど |
|
効果の持続性 |
持続的な成長促進 |
即効性が高いが持続性は低い |
バイオスティミュラントは「植物自身の能力を引き出す」ことに重点を置いているのに対し、肥料は「植物に必要な栄養素を直接供給する」ことが主な目的となります。
この違いを理解することで、それぞれの特性を活かした効果的な使用が可能になります。
使用タイミングの違い
バイオスティミュラントと肥料は、効果を最大限に発揮するための最適な使用タイミングも異なります。それぞれの特性を理解し、適切なタイミングで使用することが重要です。
<バイオスティミュラントの使用時期>
●作物の成長初期:根張りを強化し、初期成長を促進するために播種時や定植時に使用すると効果的です。丈夫な根系の形成により、その後の生育が安定します。
●ストレスが予想される時期:干ばつや病害発生が予想される前に使用することで、植物のストレス耐性を高められます。猛暑や長雨の前などが適しています。
●実際にストレスを受けた時:異常気象や病害虫の発生時など、植物がストレスを受けた際に使用することで、回復を早められます。
●収穫後:次作に向けて土壌の微生物バランスを整えるために使用することも効果的です。特に微生物系のバイオスティミュラントは土壌環境の改善に役立ちます。
<肥料の使用時期>
●植付け前の基肥:作物を植える前に土壌に混ぜ込み、初期成長に必要な栄養を確保します。
●成長段階に応じた追肥:植物の成長に合わせて追加で与える肥料。例えば野菜では生育初期、開花期、結実期など、段階に応じた追肥が重要です。
●特定の栄養素の補給:葉色の変化など栄養不足の兆候が見られた場合に、不足している特定の栄養素を補給します。
●収穫後の土壌回復:作物に消費された栄養素を補給し、次作のための土壌環境を整えます。
バイオスティミュラントは植物の機能を活性化する役割があるため、成長初期やストレス環境下での使用が特に効果的です。一方、肥料は栄養素の供給が主な目的なので、植物の成長段階に合わせた適切なタイミングでの投入が重要となります。
バイオスティミュラントのメリットとデメリット
バイオスティミュラントには多くの可能性がありますが、万能ではありません。ここでは、そのメリットとデメリットを解説します。
バイオスティミュラントは、以下のような多くのメリットが期待できます。
●環境負荷の低減
●ストレス耐性の向上
●品質の向上
●土壌環境の改善
●農薬使用量の削減
単に収益性を高めるだけでなく、環境保全や食の安全・安心といった社会的な要請にも応える、未来志向の農業を実現するための鍵となり得ます。
アグリアスでは根張りを良くして養分吸収を改善することに特化したバイオスティミュラント(エクスプルート)を取り扱っています。根系の発達を力強くサポートし、環境ストレスに負けない健やかな作物を育みます。
デメリット
一方で、バイオスティミュラントの導入や利用にあたっては、以下のような注意点や課題も存在します。
●環境要因による効果の変動
●製品ごとの効果・効能のばらつき
●導入時のコスト
これらのデメリットや注意点を理解し、特性を活かした適切な使い方を心がけることが大切です。メリット・デメリットの両面を理解することが、バイオスティミュラントを上手に活用するためのポイントとなるでしょう。
バイオスティミュラントを導入する際のポイント
実際にバイオスティミュラントを取り入れてみようと考えたとき、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。
ここでは、製品選びとコストに関する考え方のポイントをご紹介します。
製品選びのポイント
1.導入目的を明確にする
「なぜバイオスティミュラントを使いたいのか?」という目的を具体的に設定します。 「初期の根張りを良くしたい」「夏の高温ストレスを乗り切りたい」「肥料の吸収効率を上げたい」「土壌の微生物を増やしたい」「果実の糖度を上げたい」など、目的が明確であればあるほど、適した製品を選びやすくなります。
2.対象作物と栽培環境を確認する
育てている作物の種類や品種、そして自分の畑の土壌条件や栽培方法を考慮します。 製品によっては、特定の作物での効果が高かったり、特定の土壌条件での使用が推奨されていたりします。
3.成分と作用を理解する
製品ラベルや資料に記載されている主成分を確認し、それがどのようなメカニズムで植物に作用し、設定した目的に合致するかを考えます。不明な点があれば、メーカーや販売店に聞いてみるのがおすすめです。
4.使用方法や適合性を確認する
散布(葉面散布、土壌灌注)や混合(培土、肥料)、潅水チューブなど、製品によって推奨される施用方法が異なります。自分の設備や作業体系で無理なく実施できるか、また、普段使用している農薬や液肥との混用が可能かどうかも確認が必要です。
5.少量から試してみる
いきなり大規模に導入するのではなく、まずは試験的に小面積で試してみて、自分の畑や栽培方法での効果を確認することをおすすめします。効果の有無や程度、作業性などを評価した上で、本格導入を検討しましょう。
情報収集を丁寧に行い、多角的な視点から比較検討することが、最適な製品選びにつながります。
費用対効果の考え方
バイオスティミュラントの導入にはコストが発生します。その投資が、最終的にどれだけの利益(リターン)につながるかを考える「費用対効果」の視点が不可欠です。
|
評価項目 |
詳細 |
|
直接的な効果 |
● 収量増加による売上向上 ● 品質向上(等級アップ、糖度向上など)による販売価格上昇 ● 導入コストを上回る増収効果があるか試算 |
|
間接的な効果 |
● 肥料使用量削減によるコスト減 ● 異常気象による減収リスクの軽減 ● 土壌改良効果による地力向上と将来的な生産性向上 |
|
長期的視点 |
● 単年度だけでなく数年間のスパンで評価 ● 持続的な生産性向上とコスト削減効果を検討 |
|
他の栽培との相乗効果 |
● 肥培管理や土壌管理との組み合わせ効果 ● 全体の効率や収益性向上への貢献度 |
|
参考データ |
● 類似条件(地域、作物、栽培方法)での導入事例を確認 |
「製品価格が高いか安いか」だけでなく、それがもたらす様々な効果を総合的に評価し、自分の経営にとって価値のある投資となるかどうかを見極めることが大切です。
バイオスティミュラントと肥料の違いを活かそう
バイオスティミュラントと肥料は、植物へのアプローチが根本的に異なります。肥料が直接的な栄養補給の「食事」であるのに対し、バイオスティミュラントは植物本来の力を引き出す「サプリメント」や「トレーナー」のような存在です。両者は対立するものではなく、互いの長所を補い合う理想的なパートナーと言えます。
肥料による適切な栄養管理を土台とし、そこにバイオスティミュラントを賢く組み合わせることで、植物のポテンシャルを最大限に引き出し、環境ストレスに強く、高品質な作物を安定的に育てることが可能になります。
費用削減や収益向上だけでなく、環境負荷を低減する持続可能な農業にもつながるため、持続可能な農業の第一歩として期待できます。それぞれの特徴を理解し、賢く利用してみてくださいね。
なお、アグリアスでは根張りを良くして養分吸収を改善することに特化したバイオスティミュラント(エクスプルート)を取り扱っています。根系の発達を力強くサポートし、環境ストレスに負けない健やかな作物を育みます。