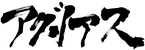肥料高騰の現状と対策!農家の収益を守る新しい選択肢とは
近年、農業を取り巻く環境はますます厳しくなっています。その中でも大きな問題となっているのが「肥料の価格高騰」です。特に2022年以降、肥料の価格は急激に上がり、多くの農家が経営の見直しを迫られています。
この記事では、肥料価格高騰の背景やその原因、農家ができる具体的なコスト削減対策について解説します。価格高騰対策としても注目されている「バイオスティミュラント」にも触れているので、農業経営に不安を抱える方はぜひ参考にしてください。
肥料価格高騰の実態
肥料価格の上昇は、農家の経営に深刻な影響を与えています。ここでは最新のデータに基づいて、実際にどの程度価格が上昇しているのか、そしてそれが農家の経営にどのような影響を与えているのかを詳しく解説します。
肥料の価格動向
農林水産省が公表している『 肥料の価格情報 』によると、2022年から2023年にかけて肥料価格は急激に上昇しました。特に2023年1月には指数が最も高くなり、その後は徐々に低下傾向にありますが、2024年に入っても、価格水準は2021年以前と比べて依然として高い状態が続いています。
JA全農の肥料価格調査『 令和6肥料年度春肥(11~5月)の肥料価格について 』を見ても、主要肥料の小売価格は2021年と比較して価格上昇が見られています。
価格推移は、肥料の種類(窒素・リン酸・カリなど)を問わず、全体的な傾向として見られています。指数での推移のため、実際の価格(円ベース)は示されていませんが、農家が日々感じている「高止まり」の実感は、このデータからも裏付けられるといえるでしょう。
農家経営への影響
肥料価格の上昇は、農家の収益に直接的な影響を与えています。生産コストに占める肥料費の割合は作物によって異なりますが、農業を営む上で重要な経費項目となっていることは確かです。
特に施設園芸や露地野菜など、肥料投入量の多い作物では影響が大きく、肥料価格の高騰は利益率の低下を招いています。また、価格変動の予測が難しいことから、営農計画の立案にも支障をきたしています。
肥料価格高騰の原因
肥料価格上昇の背景には、以下のような要因が考えられます。
●エネルギー価格の上昇
●原料供給の不安定化
●円安の影響
それぞれ詳しく解説します。
エネルギー価格の上昇
肥料の価格が上がった大きな理由の一つが、「エネルギー価格の上昇」です。特に窒素肥料の製造には大量の天然ガスが使われており、ガス価格が上がれば、そのまま肥料の製造コストも跳ね上がります。
2022年には、ロシア・ウクライナ情勢の影響で、世界的に天然ガスの供給が不安定になり、価格が急騰しました。これにより、肥料価格も連動して大幅に上昇したのです。
窒素肥料の主原料となるアンモニアの製造過程では、天然ガスが原料と製造エネルギーの両方として使用されます。肥料業界の試算によると、窒素肥料1トンの製造には約1トンの天然ガスが必要とされています。
2021年末から2022年にかけて、欧州の天然ガス価格は一時的に高騰し、アジア市場でも2倍以上に上昇しました。その後、2023年から2024年にかけては落ち着きを見せたものの、ウクライナ情勢の長期化により、依然として高値で推移しています。
原料供給の不安定化
日本は肥料の主要な原料を、ほとんど海外からの輸入に頼っています。たとえば、カリ肥料の原料となる塩化カリウムはカナダやロシア、リン酸肥料は中国やモロッコからの輸入が多いです。
こうした特定国への依存は、国際的な紛争や輸出制限の影響を直接受けるリスクがあります。実際に、中国は2022年にリン酸肥料の輸出を一時制限し、日本への供給が不安定になる事態が発生しました。
輸入がメインの肥料の原材料は、世界情勢によって左右されるため安定した価格での仕入れが難しいのは事実です。
円安の影響
日本円の価値が下がる「円安」も、肥料価格を押し上げる大きな要因になっています。2022年から2023年にかけて円安が進み、1ドル=150円前後まで落ち込んだことで、輸入品の価格が全体的に高騰しました。
肥料の原料や製品を海外から仕入れている日本にとって、為替の影響は非常に大きく、農業資材全体のコスト増加につながっています。
2021年初めには1ドル=103円程度だった為替レートが、2023年秋には一時151円を超える水準まで円安が進行しました。これは約47%の円安であり、仮に海外の肥料価格が変わらなかったとしても、円ベースでは47%の価格上昇になります。
2024年に入ってからは、やや円高方向に振れる場面もありましたが、依然として1ドル=140円台で推移する時期も多く、円安による輸入コスト増加の問題は解消されていません。
肥料高騰に対するコスト削減対策
肥料の価格が高騰している中で、従来の使い方を見直すだけでもコスト削減につながります。ここでは、肥料の使い方を工夫することで実現できる節約方法と、活用できる支援制度について詳しく紹介します
土壌診断に基づく適正施肥
多くの農地では、長年の慣行的な施肥により、特にリン酸やカリウムが蓄積していることがあります。土壌診断を行うことで、実際に不足している栄養素だけを補うことができ、無駄な肥料を削減できるため、コスト削減効果が期待できるでしょう。
【土壌診断の方法】
●農協や都道府県の農業試験場、民間の検査機関に依頼する
●自分で行える簡易土壌診断キットで検査する
●最新のセンサー技術を活用した検査で土壌分析をする
土壌診断の結果に基づいて肥料量を見直した農家では、肥料コストを削減しながら、収量や品質を維持できたケースもあります。特にリン酸やカリの蓄積が見られる畑では、これらの成分を減らした肥料設計に切り替えることで、大幅なコスト削減が可能です。
肥料の種類・使用方法の工夫
肥料の使用方法を工夫することで、コスト削減が可能です。主な工夫として以下のような方法があります。
|
緩効性肥料の活用 |
● 通常の肥料より価格は高めだが、効果が長く続く ● 総施肥回数と総量を減らすことが可能 ● 水稲や長期栽培の野菜に効果的 ● 最新の緩効性肥料は溶出パターンの制御が可能 |
|
局所施肥によるコスト削減 |
● 植物の根元周辺にピンポイントで肥料を与える方法 ● 畝立て栽培では肥料使用量を30〜40%削減可能 |
|
有機質肥料の活用 |
● 堆肥や緑肥などの有機質資材を活用 ● 土壌の物理性改善と養分保持力向上 ● 近隣の畜産農家から入手できる家畜糞尿の活用 ● レンゲやクローバーなどの緑肥作物の導入 |
環境整備や肥料の代替など、方法はさまざまです。農作物の特徴や環境を考慮した対策を選びましょう。
補助金・支援制度の活用
肥料高騰に対して、国や自治体も支援制度を用意しています。たとえば、農林水産省では「肥料価格高騰対策事業」などを実施しており、条件を満たせば補助金を受け取ることができます。
【主な補助内容】
●土壌診断にかかる費用の補助
●肥料コスト削減のための機材導入補助
●堆肥や有機質肥料への転換支援
●化学肥料削減に取り組む農家への直接支援
支援制度は年度や地域によって異なるので、こまめに自治体やJAの情報を確認することが大切です。
肥料高騰に立ち向かう新たな選択肢「バイオスティミュラント」
肥料価格の高騰に対する新たな対策として、世界的に注目を集めているのが「バイオスティミュラント」です。ここでは、バイオスティミュラントの基本的な情報と、その活用によるメリット、選び方のポイントについて解説します。
バイオスティミュラントとは何か
「バイオスティミュラント(Biostimulant)」は、欧米ですでに多くの農家が活用している次世代の農業資材です。簡単に言えば、作物の「生命力」や「環境ストレスへの耐性」を高めてくれる資材のことで、肥料とは異なるアプローチで収量や品質向上を目指します。
微生物・海藻エキス・アミノ酸・腐植物質など、天然由来の成分が使われており、環境への負荷が少ない点も注目されています。
バイオスティミュラント選びのポイント
バイオスティミュラントを選ぶときは、自分の育てている作物に合った製品を選ぶことが大切です。例えば、じゃがいもやにんじんなどの根菜類にはフミン酸系や微生物系が効果的で、トマトやキュウリなどの果菜類には複合型が向いています。
製品を選ぶ際は、具体的な試験データを公開していたり効果の仕組みをきちんと説明していたりするものがおすすめです。利用者の口コミや公的機関の研究結果を参考にして選ぶとよいでしょう。
また、導入前には必ず使用方法や時期が自分の農作業に合っているか確認することが大切です。今使っている農薬や肥料と一緒に使えるか、費用に見合う効果が期待できるか確認しましょう。初めから全体に使用するのではなく、一部分だけで試してみると安心です。
肥料高騰は別アイテムで対策を
肥料価格の高騰は、エネルギー価格上昇、原料供給の不安定化、円安の影響など複合的な要因によるものであり、短期間での価格下落は期待しにくい状況です。そのため農家の皆さんは、複数の対策を組み合わせて対応することが求められるでしょう。
さまざまな対策の中でも「バイオスティミュラント」は、コスト削減だけでなく、環境や品質、気候変動対応など多面的なメリットがあります。今後の農業経営において有効な選択肢となるため、検討してみる価値があります。
なおアグリアスでは、日本の農業環境に適したバイオスティミュラント製品を取り扱っています。興味のある方は、商品ページをご覧いただくかお気軽にお問い合わせください。