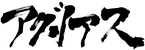きゅうりの葉が枯れる6つの原因と対策を解説!根から強くする方法とは

「一生懸命育てているきゅうりの葉っぱが急に枯れてきた...」
「せっかく実がつき始めたのに、葉が黄色くなって心配」
そんな経験はありませんか?
きゅうりの葉が枯れる現象は、収穫量や品質に直結する問題です。
この記事では、葉が枯れる原因の特定から具体的な対策、根本的な解決策まで解説します。
葉枯れの原因や対策を理解して、健康で丈夫なきゅうりを育てましょう。
きゅうりの葉枯れが及ぼす収穫量・品質への影響

きゅうりの葉枯れによる影響は、収穫量の減少だけではありません。品質面や経営面など、さまざまな面で影響が生じます。
| 影響の種類 | 具体的な被害 | 経営への打撃 |
|---|---|---|
| 即座の影響 | ・収穫量の減少 ・果実の変形・変色 ・糖度低下、苦味発生 |
売上直撃 |
| 長期的な影響 | ・株の免疫力低下 ・来期の生育不良 ・土壌病害菌の蓄積 |
翌年以降も継続被害 |
「少し枯れただけだから様子見」「原因不明だから放置」といった判断は危険です。1週間の対応遅れが1シーズンの収益悪化につながります。
葉っぱは光合成を担っており、枯れると生育ストップから品質・収量激減の悪循環に陥ります。しかし、早期発見・早期対策で多くは回復可能です。
まずは冷静に観察し、適切な対策を講じることが大切です。
きゅうりの葉が枯れる6つの原因とは

きゅうりの葉が枯れる原因は、水やりや肥料の問題や病害虫の被害、そして畑の環境まで、多岐にわたります。
きゅうり畑で今何が起きているのか、その原因を一つずつ探っていきましょう。
水分ストレス
きゅうりは水分を多く必要とする野菜ですが、適切な水分管理ができていないと、葉が枯れる原因になります。水分ストレスには「水不足」と「水過多」の2つのパターンがあります。
①水不足による葉枯れの症状
- 葉がぐったりとしおれる
- 葉先から茶色く枯れ込む
- 土の表面がひび割れている
水不足が続くと、きゅうりは自分の身を守るために古い葉から水分を奪い、新しい葉や実に回そうとします。その結果、下葉から順番に枯れていくのです。
②水過多による葉枯れの症状状
- 葉が黄色くなって落ちる
- 根元付近の土から嫌な臭いがする
- 株全体の元気がない
水をやりすぎると、土の中の酸素が不足して根が呼吸できなくなります。この状態が続くと根腐れを起こし、栄養や水分を吸収できなくなって葉が枯れてしまいます。
<正しい水やりのポイント>
- 土の表面から2~3cm下を指で触って判断
- 朝の涼しい時間帯に根元へたっぷりと
- 1回の水やりで土の奥まで浸透させる
水やりは「土が乾いたらたっぷり」が基本です。毎日少しずつではなく、メリハリをつけた水やりが根の健康を保つコツです。
栄養不足・過剰
きゅうりが健康に育つためには、窒素・リン酸・カリウムの3つの主要栄養素がバランスよく必要です。どれかが不足しても、逆に多すぎても葉枯れの原因になります。
①主要栄養素の欠乏症状
- 窒素不足:下葉から黄色くなって枯れる
- リン酸不足:葉が紫がかった色になる
- カリウム不足:葉の縁が茶色く焼けたようになる
窒素が不足すると、きゅうりは古い葉の窒素を新しい葉に移動させるため、下葉から黄色くなって枯れていきます。リン酸不足では光合成がうまくいかず、カリウム不足では細胞の水分調節ができなくなります。
②肥料過多(肥料焼け)の症状
- 葉の縁が茶色く枯れる
- 根が黒くなって腐る
- 急激な成長停滞
肥料が多すぎると、土の中の塩分濃度が高くなり根が水を吸収できなくなります。これを「肥料焼け」と呼び、深刻な場合は株全体が枯れてしまいます。
<適切な施肥のポイント>
- 土壌診断で現在の栄養状態を把握
- 緩効性肥料で安定した栄養供給
- 追肥は株の状態を見ながら調整
土壌や葉の観察をすることで、何が不足しているのか、何が過剰なのかを判断できます。状況にあった対策をすることが大切です。
病気や害虫の被害
病気や害虫は、きゅうりの葉枯れの原因として非常に多いケースです。早期発見・早期対処が被害を最小限に抑えるポイントです。
<代表的な病気と症状>
- うどんこ病:葉に白い粉状のカビ
- べと病:葉に黄色い角張った斑点
- 炭疽病:葉に茶色い円形の斑点
- 萎凋病:株全体が急にしおれる
うどんこ病は湿度が高く、風通しが悪い環境で発生しやすく、放置すると葉全体が白くなって枯れます。べと病は雨が多い時期に発生し、葉に黄色い斑点ができて最終的に枯れます。
<主な害虫と被害>
- アブラムシ:葉の栄養を吸って黄化させる
- ハダニ:葉に小さな斑点を作る
- コナジラミ:葉を吸汁して弱らせる
これらの害虫は葉から栄養を吸い取るだけでなく、ウイルス病を媒介することもあります。特に高温乾燥期には爆発的に増殖するため、注意が必要です。
<早期発見のチェックポイント>
- 毎朝の葉裏チェック
- 新芽周辺の観察
- 株元の状態確認
病気や害虫は初期段階での発見・対策が重要です。毎日の観察を習慣化し、変化に気づいたらすぐに対処しましょう。
環境ストレス
きゅうりは温度や日照に敏感な野菜です。適切な環境から外れると、すぐに葉に症状が現れます。
①高温による障害
- 症状:葉が焼けたように茶色くなる、日中にぐったりしおれる
- 原因:35℃以上の高温、強すぎる直射日光
- 対策:遮光ネット、こまめな水やり
真夏の強い日差しは葉を直接傷つけ、焼けたような症状を引き起こします。また、高温により蒸散が活発になりすぎると、水分供給が追いつかずしおれてしまいます。
②低温による障害
- 症状:成長が止まる、葉が紫色になる
- 原因:15℃以下の低温、急激な温度変化
- 対策:防寒対策、トンネル設置
きゅうりは寒さに弱く、15℃以下になると生育が止まります。特に夜間の冷え込みは葉に紫色の変色を起こし、最終的に枯れにつながります。
③日照不足による障害
- 症状:葉が薄い緑色になる、軟弱な成長
- 原因:曇天続き、遮蔽物による日陰
- 対策:反射シート設置、栽培場所の見直し
日照不足では光合成が十分にできず、葉が薄い緑色になって軟弱に育ちます。この状態では病気にもかかりやすくなります。
生理障害
生理障害は外部から見えにくい問題ですが、葉枯れの原因として見落とされがちです。
肥料焼けのメカニズム 濃度の高い肥料が根に直接触れることで、浸透圧の影響で水分が逆流し、根が傷んでしまいます。特に化成肥料を大量に施用した場合や、有機肥料が未熟な状態で使用された場合に起こりやすくなります。
<根の損傷による影響>
- 定植時の根切れ
- 土壌の固化による根張り不良
- 過湿による根腐れ
定植作業で根を傷つけてしまうと、水分や栄養の吸収能力が低下し、葉が枯れる原因になります。また、土が固いと根が十分に張れず、健全な生育ができません。
<対策のポイント>
- 肥料は適量を土と十分混和
- 定植時は根を丁寧に扱う
- 土壌の物理性改善(排水性・通気性)
肥料は一度に大量に施用せず、土とよく混ぜて使用することが重要です。また、定植時は根を傷つけないよう注意深く作業しましょう。
連作障害
「連作障害」とは 同じ場所で同じ科の作物を続けて栽培することで起こる生育不良のことです。土壌中の特定の栄養素が偏って減少したり、病害菌が蓄積したりすることが原因です。
<きゅうりの連作障害の症状>
- 生育が悪くなる
- 病気にかかりやすくなる
- 収穫量が減少する
きゅうりはウリ科の植物で、同じ科の野菜(メロン、スイカ、カボチャなど)を続けて栽培すると連作障害が起こりやすくなります。特に2年目以降は症状が顕著に現れます。
<対策方法>
- 3~4年の輪作を実施
- 土壌消毒や土壌改良
- 異なる科の作物との組み合わせ
最も効果的な対策は輪作です。ウリ科以外の作物(トマト、ナス、豆類など)を組み合わせることで、土壌環境を改善できます。
きゅうりの葉枯れを根本解決!根の健康が収穫量を左右する理由

きゅうりの葉枯れを根本から解決するには、地下部の根の健康に注目することが必要です。
ここでは、なぜ根の健康が収穫量に直結するのか、そして従来の対策では限界がある理由を詳しく解説します。
根の健康=植物全体の健康
きゅうりの根は、人間でいえば「胃腸」と「血管」の両方の役割を果たしています。根が健康でなければ、どんなに上手に栽培しても期待する収穫は得られません。
<根の働きと植物への影響>
| 根の状態 | 植物への影響 | 収穫への影響 |
|---|---|---|
| 健康な根 | ・水分・栄養を効率よく吸収 ・植物ホルモンを活発に生産 ・光合成能力が向上 |
・糖度の高い果実 ・花つきが良い ・収量アップ |
| 弱った根 | ・吸収能力が低下 ・ホルモン生産が減少 ・光合成がうまくいかない |
・味が悪くなる ・実がつきにくい ・収量ダウン |
根系の発達と収穫量の関係 根の表面積や体積が大きいほど、栄養吸収能力が向上します。つまり、根をいかに健康に育てるかが収量アップの近道です。
<健康な根がもたらす3つのメリット>
- 干ばつ耐性:深く広く張った根が土壌深部から水分を確保
- 強風耐性:しっかりした根が台風などの悪天候に耐える
- 持続的生産:栄養吸収能力が高く、長期間安定して収穫可能
なぜ従来の対策では不十分なのか?
多くの農家が実践している従来の対策は、主に「症状への対処」に重点を置いています。しかし、これだけでは根本的な解決にはなりません。
①病気や害虫だけに注目してしまいがち
葉に異常が見つかると、まず病気や害虫を疑うのが一般的です。
確かに薬剤散布で一時的に症状は改善されますが、根の健康状態が悪ければ、再び同じ問題が発生します。
病気に強い植物を育てるには、薬剤に頼るだけでなく、植物自体の免疫力を高めることが必要です。そのためには、根の健康が欠かせません。
②「根圏環境」や「微生物との共生」が見落とされている
根の周りの環境を「根圏」と呼びます。この根圏には無数の微生物が住んでおり、植物と複雑な関係を築いています。有益な微生物は植物の栄養吸収を助け、病原菌から守ってくれます。
しかし、化学肥料や農薬の多用により、この微生物バランスが崩れることがあります。その結果、根の機能が低下し、葉枯れなどの問題が発生しやすくなります。
現代の農業には、根圏環境を整え、微生物との共生を促進する新しいアプローチが求められています。
きゅうりを根から強くする技術「バイオスティミュラント」とは?

近年、農業界で注目されている「バイオスティミュラント」をご存知ですか?
これは植物の生理機能やストレス耐性を高める革新的な資材で、従来の農薬や肥料とは全く異なるアプローチで植物を強化します。
バイオスティミュラントは、植物が本来持っている力を最大限に引き出すことで、健康で丈夫なきゅうりを育てることができます。ここでは、この画期的な技術について詳しく解説します。
バイオスティミュラントとは?従来の農業資材との違い
バイオスティミュラントは「生物刺激剤」とも呼ばれ、植物の生理機能を活性化させる新しいタイプの農業資材です。
<バイオスティミュラントの定義>
植物に直接的な栄養を与えるのではなく、植物が持つ本来の力を引き出し、健康で丈夫な植物を育てるための資材。海藻エキス、腐植酸、アミノ酸、微生物などの天然由来成分が主原料となっています。
<従来の農業資材との違い>
- 農薬:病害虫を直接退治する
- 肥料:植物に栄養を与える
- バイオスティミュラント:植物自身の力を強化する能
農薬は病害虫という「敵」を攻撃し、肥料は植物という「味方」に栄養を補給します。一方、バイオスティミュラントは植物の「体質」や「生育環境」を改善し、生命力を高める働きがあります。
<きゅうり栽培での具体的効果>
- 根系の発達促進で栄養吸収力アップ
- 環境ストレス耐性の向上
- 病害抵抗性の強化
- 光合成能力の向上
- 収量・品質の安定化
バイオスティミュラントを使用することで、きゅうりは厳しい環境でも安定して生育し、高品質な果実を継続的に生産できるようになります。
農家がバイオスティミュラントに注目する理由
現代の農業は、気候変動や土壌劣化、消費者の安全志向など、従来の方法だけでは対応が困難な問題が増えています。
<現代農業が抱える課題>
- 異常気象による環境ストレス増加
- 連作による土壌疲弊
- 持続可能な農業への要求
- 高品質作物への需要拡大
近年の夏は猛暑が続き、冬は予想以上の寒波が襲来するなど、きゅうりにとって過酷な環境が常態化しています。また、同じ畑で何年も栽培を続けることで土壌が疲弊し、収量や品質の低下が問題になっています。
<バイオスティミュラントが解決する問題>
- 化学肥料や農薬に頼りすぎない栽培
- 環境変化に強い作物の育成
- 安定した収量と品質の確保
- 土壌環境の改善
バイオスティミュラントは、植物自体を強くすることで外部環境の変化に左右されにくい安定した栽培を可能にします。
きゅうり栽培でのバイオスティミュラント活用法
バイオスティミュラントの効果を最大限に引き出すには、適切なタイミングと方法で使用することが重要です。
<使用のタイミング>
- 育苗期:根系発達促進のため苗の段階から
- 定植時:活着促進と初期生育強化
- 生育期:継続的な体質強化(月1~2回)
- ストレス時:高温期や病気の予防として
育苗期から使用することで、根系の発達が促進され、定植後の活着が良くなります。生育期間中は定期的に使用することで、継続的な体質強化が図れます。
<具体的な使用方法>
- 土壌灌水:水に希釈して根元に施用
- 葉面散布:朝夕の涼しい時間に散布
- 育苗培土混合:苗作りの段階から活用
最も効果的なのは土壌灌水です。根に直接働きかけることで、根系の発達と微生物活性の向上が期待できます。葉面散布は即効性があり、ストレス時の応急処置としても活用できます。
根系発達を促進する製品として、「エクスプルート」のような腐植酸系バイオスティミュラントが効果的です。バイオスティミュラントや土壌に関する情報は、アグリアスのブログでも紹介しています。
きゅうりの葉枯れを乗り越え、豊かな収穫を目指そう!
きゅうりの葉枯れを防ぐには、毎日の観察が欠かせません。枯れてしまった原因を見極めた早期対策が重要になります。
しかし、理想は枯れない予防をすること。「根っこから強いきゅうり」を育てることです。
健康な根は病気に強く、環境ストレスにも負けません。従来の対症療法的なアプローチから、予防的で根本的なアプローチへと転換することが、安定した収量と品質の確保につながります。
健康で美味しいきゅうりを育てて、豊かな収穫を叶えましょう!