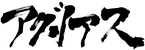農業に役立つ土壌学1~土壌学とは?~
目の前に灰色の砂と黒い土があります。植物を育てるとしたら、どちらを選ぶでしょうか。

確かな根拠はなくても、黒い土を選ぶという人が多いのではないかと思います。
砂と比べると、畑や森などの土は黒っぽくてふかふかとしていますし、なんとなく植物が良く育つ印象があるのではないでしょうか。実は、この「黒っぽい」ことと「ふかふかとしている」ということが、植物の生育を支える土の特徴と密接に関係しているのです。
そもそもなぜ土は黒くてふかふかなのか、そしてこうした特徴がどのように植物の生育と関係しているのか見ていきましょう。
1.土はなぜ黒い?
土は様々な大きさの無機粒子と有機物が混ざったもので、この有機物が黒っぽさの由来です。
土の原材料である岩石(母岩と呼びます)は、まず水分や温度の変化が繰り返され(機械的風化)、さらに大気や水に含まれる炭酸イオンなどの物質との化学反応(化学的風化)によって細かく砕けていき、土のもととなる「母材」となります。すると、だんだんとここに炭素や窒素を自分で調達できるような生物(ラン藻などの微生物、地衣類(菌類と藻類の共生体)など)が棲みつき始めます。そうした生物の遺体が有機物として母材に蓄積することで、岩石由来の無機粒子と有機物が混ざり始めるのです。母材の風化と生物による有機物の供給が繰り返され、次第に地衣類よりも発達したコケなどの植物が育つことができるようになっていきます。そうなると、微生物に加えて土壌動物と呼ばれる体の大きな生物も棲めるようになります。そうしてさらに風化と生物による土壌生成作用が繰り返され、長い年月をかけて黒っぽい色の土が形成されるのです(図1)。わずか1cmの土が作られるのに100年から1000年もの月日が必要だと考えられています。

2.有機物と土の粒子が作る構造:団粒

土は有機物が含まれることによって、岩石由来の無機粒子だけでは形成できない複雑な構造を作り上げています。
土の原材料である岩石は、風化の過程で様々な大きさの粒子になります(図2)。
大きい順に礫、砂、シルト、粘土と呼びますが、土壌学では砂よりも小さい粒子のことを土壌と呼んでいます。また、粘土は風化の過程で岩石から溶け出たケイ素やアルミニウムなどが再結晶して作られる粒子(二次鉱物)が大半です。
これらの粒子は有機物や微生物(カビの菌糸や細菌が細胞外に分泌する粘着性の物質)を接着剤としてくっつき、「団粒」と呼ばれる塊を作ります。粘土やシルトなどの小さな粒子がまず集まって「ミクロ団粒」という小さな団粒を作り、さらにミクロ団粒や砂が集まって「マクロ団粒」を形成します(図3)。

実際に畑の土を乳鉢で粉砕し、団粒を壊すことでどのくらい孔隙が減るのか調べてみました。
団粒を粉砕した土と粉砕していない土をそれぞれ10gずつメスシリンダーに入れると、13mlあった体積が粉砕によりに減りました。つまり、団粒により2mlの孔隙が作られていたことになります(図4)

このさまざまな大きさの孔隙は、のちに説明するように土の排水性や保水性、根への酸素供給に影響し、さらに多様な生物の生息場所としても重要な役割があります。土壌生物については、第2回から第4回にかけて注目します。
3.作物生育を支える土の特性
土の特徴である黒っぽさやつぶすと次々と壊れていく団粒構造が有機物によるものであることは見てきました。ではなぜ土では植物が良く育つのでしょうか。
3-1.養分の保持・供給

粘土粒子や有機物の多くは、マイナスの電荷を帯びています(プラスの電荷を帯びていることもあります)(図5)。マイナスの電荷を帯びている粘土や有機物は、プラスの電荷をもつ物質が引き寄せられ、くっつくことができます。このメカニズムにより、土は土中の水に溶けている養分を保持しているのです。保持される養分には、例えばアンモニウムイオン(NH4+)やカリウムイオン(K+)などがあります。ただし、こうして土に引き寄せられた養分は、ずっと保持されるわけではありません。植物によって土中の水に溶けている養分が吸われると、それに応じて保持されていた養分の一部が土中の水へと溶け出していきます。このようにして、土は余分な養分を貯めることができる一方で、必要な時には植物へと供給することができるのです。
一方、マイナスの電荷を帯びている粒子には、マイナスの電荷を帯びた養分は引き寄せられません。そのため、施肥された窒素は畑では最終的に硝酸イオン、つまりマイナスイオンになり土に保持されることなく流れてしまいます。畑からの硝酸イオンやリン酸イオンといった栄養塩類の溶脱はたびたび問題になっていますが、これが理由の一つです。
3-2.水分の保持・供給
水は小さな孔隙には強い力で保持される一方で、大きな孔隙からは簡単に流れていきます(図6)。
例えば、水に浸けたタオルを絞る場面を想像してみて下さい。どれだけ強く絞ってもタオルは水で濡れています。これは、繊維と繊維の小さな孔隙に水が強い力で保持されているためです。反対に、大きな孔隙にあった水は絞ると流れていきます。
土の場合でも、小さな粒子が多く含まれる土ほど小さな孔隙が多くなり、水を保持する力が強くなります(図6)。そのため、多くの水を保持できるようになりますが、粘土のように非常に小さな粒子の表面に保持された水は保持される力が強すぎてしまい、植物も簡単に吸うことはできないということがおきるのです。そのため、粘土だけからなる土では土に含まれる水分量自体は多いのですが、植物が利用できる水はかならずしも多くないということになります。逆に、粒子が大きな土はたくさんの水を保持することができない分、排水性は良くなります。

土の粒子は有機物や微生物を接着剤としてくっつき、大小さまざまな孔隙を含む団粒を作ることはすでに述べました。これは、水を保持する力の強い小さな孔隙もあれば、排水性の良い大きな孔隙もあることを意味しています(図7)。排水性が良いということは、土の中に空気が多いということです。根の生長には酸素が必要であり、排水性は水稲やレンコンといった水生植物以外では、すべての植物の生育に重要です。
3-3.有機物の分解と養分供給
例えば落ち葉など、土に入ってきた有機物はさまざまな生物の活動によって分解されていきます(図8)。まず、ミミズなどの体の大きな土壌動物が有機物を砕き、それを微生物がさらに細かく分解していきます。そうして一部の有機物は無機態まで分解され、植物が養分として利用できるようになります。
森林では肥料をまったく入れないのにも関わらず、背の高い樹木が生い茂っています。このことに疑問を持ったことがある方も多いのではないでしょうか。それは、落ち葉や根など、樹木から土に供給された有機物が分解されて、無機化された養分を樹木が再利用しているからなのです。
ところで、植物は落ち葉そのものを養分源として利用することはできません。同様に、落ち葉だけでは団粒を作ることもできないのです。植物への養分供給だけではなく団粒を形成するためにも、有機物が分解される必要があります。有機物の機能を引き出すには、生物による分解が欠かせないのです。

土の中にいる生物は有機物の分解以外にも植物の生育促進や病害防除など、様々な貢献をしています。そんな土壌生物については第2回で、さらに詳しく微生物(第3回)と線虫(第4回)について注目していきます。第5回では、土壌生物にもっとも影響する農薬である燻蒸剤、そのあとは肥料や微量元素について(第6、7回)、第8回では、土壌生物機能を促進すると言われるバイオスティミュラントについて注目する予定です。
引用および参考文献
石黒宗秀. 2015. 3-5 土の孔隙と保水・排水―水を吸う土・はじく土―.土のひみつ 食料・環境・生命. p.70-73. 朝倉書店
松中照夫. 2018. 土壌学の基礎 生成・機能・肥沃度・環境. 農文協
谷昌幸. 2015. 1-2 土の粒径と土性. 土のひみつ 食料・環境・生命. p.6-9. 朝倉書店
Weil, R.R. and Brady, N.C., 2016, The Nature and Properties of Soils, Pearson